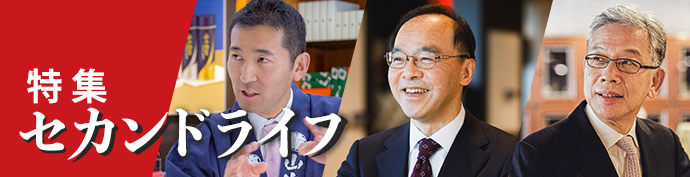遺贈にかかる税金の種類や計算方法とは?死因贈与との違いも解説
遺贈とは、遺言書で意思表示をすることにより、自分の財産を贈りたい相手を指定して譲渡することです。今回は、遺贈の種類や課税される税金、注意点などを解説しまう。納税額の多寡によっては、せっかくの財産相続を放棄したり、現金で納税できずに物納となることもあるので、しっかりと準備しておきましょう。

「遺贈(いぞう)」とは、遺言に従って相続財産を相続人、あるいは第三者の個人や法人などに、無償で譲渡することです。相続では、法律に従って相続財産を法定相続人で分割して引き継ぎますが、遺贈では遺言書に従って財産の全部、もしくは一部を法定相続人やほかの親族、第三者の個人、団体などに譲渡することができます。
また、遺贈には相続税をはじめ、さまざまな税金がかかります。法定相続人以外へ遺贈するケースでは、通常の相続税より高額になるため要注意です。不動産を現金化せずに引き継ぐケースなどでは、税金の納付に必要な多額の現金を用意しなければなりません。遺贈はただで相続を受け取るだけでは終わらないため、譲渡する際には受け手の負担にならないよう、十分な配慮が求められます。

遺言書の種類を解説!種類別のメリットとデメリット、気になる費用も解説

法定相続人はどんな順位できまる?遺産の取り分や例外での注意点を解説
遺贈と相続の違い
遺贈と相続は、どちらも死亡した者の財産を譲渡・受納することを指しますが、財産の受け手が異なります。相続では、原則的に法定相続人(配偶者・子供・両親・兄弟姉妹など)ですが、遺贈では遺言で指名されている者や法人などです。遺贈の場合は「受遺者(じゅいしゃ)」と呼ばれ、受遺者になることに条件や制限はありません。つまり、法定相続人のほかに、血縁関係のない第三者や団体、法人なども受遺者になることができます。
不動産を相続する際は、相続した相続人が不動産登記を申請しますが、遺贈では受遺者のみではなく、相続人全員との共同による登記申請が欠かせません。遺言執行者が決まっている場合は、受遺者と遺言執行者のみでも申請が可能ですが、手続きは相続時よりも複雑です。
遺贈にも相続と同様に「相続税」の納付が課せられており、法定相続人以外の者が財産を受納した場合は、法定相続人よりも納める相続税額が増加します。また、遺贈は相続時ではかからない「不動産取得税」がかかるだけでなく、不動産の相続登記に必要な登録免許税も相続時より高額になる点に注意しましょう。

【義務化】「相続登記」とは?不動産の相続に必要な手続きや費用について

遺言執行者(遺言執行人)とは?役割や権限や資格等、わかりやすく解説
遺贈と死因贈与の違い

遺贈によく似ているケースに「死因贈与」があります。死因贈与とは、生前に財産の受け手を指名しておき、死亡を原因として生じる財産の譲渡契約です。遺贈では受け手の承諾は不要ですが、死因贈与の譲渡の契約を結ぶために、受け手の承諾をもらわなければなりません。さらに、遺贈では遺言書が必要ですが、死因贈与では書類のない口頭の約束でも契約が成立します。
また、遺贈を決定する遺言は、一度作成した後でも書き直しできるので、遺贈の内容は以後の撤回が可能です。死因贈与も民法の遺贈の規定に準じており、基本的には決定した内容の撤回が認められていますが、契約者が譲渡を条件に譲渡者の生活をサポートするなどの負担を課されている「負担付き死因贈与」の場合は、撤回が却下されることも考えられるでしょう。
税金面では、死因贈与も死亡を原因として財産を受納するため、贈与税ではなく相続税が発生する点は相続や遺贈と同様です。ただし、死因贈与では対象が法定相続人であっても、不動産取得税と登録免許税の税率が遺贈の第三者の場合と同率です。
遺贈には2種類ある

遺贈には、相続財産の割合を限定する「包括遺贈」と、財産の内容を限定する「特定遺贈」の2種類の手段があり、それぞれ特徴が異なります。
包括遺贈
「包括遺贈」とは、簡単にいえば遺贈する財産の割合を決めておく手段です。例えば、遺言書における「すべての財産をAに与える」「全財産の30%をBに譲る」などのように、財産の内容を限定せず、全部もしくは一定の割合を限定して指名した者に譲渡します。
財産の全部、もしくは一定の割合を遺贈するため、相続財産に負債がある場合は、資産のみではなく負債も遺贈の対象です。遺贈の割合が決められているケースでは、プラスの資産と等しい割合で負債も分割され、支払いの義務を引き継がなければなりません。
また、一定割合の包括遺贈は分割手段がはっきりしておらず、遺産分割協議において、ほかの相続人とのトラブルが生じやすい点に要注意です。包括遺贈は相続の承認・放棄には、相続人と同じ規定が応用されることから、3ヶ月の期限があります。もし、受遺者が遺贈をそのまま受納するつもりがない場合は、期限内に「相続放棄」や「限定承認」の申し立てが必要です。

相続放棄とは?遺産の価値や限定承認も検討して放棄すべきか考えよう

相続の限定承認とは?相続放棄との違いや複雑な手続きの流れを解説
特定遺贈
「特定遺贈」とは、一言で表せば、遺贈する財産の内容を決めておく手段です。例えば「〇〇銀行〇〇支店の定期預金、口座番号〇〇〇をAに与える」「〇〇県〇〇市〇〇町1丁目1番地の土地と建物をBに譲る」などのように、財産の内容を明確にして指名した者に譲渡します。
特定遺贈は相続の承認・放棄の期限が設けられていないため、受遺者が特定遺贈を認識してから、承認・放棄をするまでに何年かかっても問題ありません。ただし、遺贈義務者など権利を有する関係者が、回答期限を設けた場合は、回答がないまま期限を過ぎると、遺贈が承認されたとみなされる仕組みです。承認・放棄の期限はないものの、承認前に財産が失われた場合は、遺贈の事実が無効になってしまいます。また、株式を譲渡するケースでは、原則として承認の手続きが欠かせません。
不動産を譲渡するケースにおいて、受遺者が法定相続人の場合は不動産取得税の納付が不要ですが、ほかの第三者の場合は納付義務が生じます。相続財産の内容を限定する「特定遺贈」では、その財産の価値が高い場合は、ほかの相続人の遺留分が侵害されて、トラブルになるおそれがあるため注意しましょう。
遺贈の相続税の算出方法

遺贈や相続に関係なく、相続税は死亡した者の相続財産を受納した際に、基礎控除額の超過分の金額に対して税金がかかります。相続財産の合計額が基礎控除を超過していない分には、相続税がかからないため、はじめに基礎控除額を算出します。
遺贈の場合は、受遺者が法定相続人かほかの第三者かによって相続税額が異なるので要注意です。第三者の相続税額は、法定相続人の税額に比べて2割分が加算された金額になることから、法定相続人の相続税額総額の算出後に、第三者の納付が必要な相続税額を導き出せます。
出典【遺贈の相続税の算出手順】
1.基礎控除額の算出
2.基礎控除額の差し引き算出
3.課税対象額の算出
4.相続人各人の受納額の算出
5.税額軽減措置として各種の控除
6.法定相続人以外の第三者の相続税
【参照】国税庁「No.4152 相続税の計算」詳細はこちら
1.基礎控除額の算出
はじめに行う基礎控除額の算出は、下記の公式に当てはめます。
「基礎控除額=3,000万円+(600万円×法定相続人の数)」
法定相続人は民法に従って、配偶者→子供→父母→兄弟姉妹と、相続順位が決められており、その上位の者から相続権の獲得が可能です。死亡した者の家族構成により、法定相続人の順位や数が変わることがあるでしょう。相続を放棄した者がいる場合、放棄した人数も法定相続人の数に含めなければなりません。
例えば、配偶者と子供がいるケースでは、法定相続人は配偶者と子供を合わせた人数です。配偶者と子供が二人いる場合の基礎控除額は、前述した公式に当てはめて「3,000万円+(600万円×3)=4,800万円」と算出できます。
2.基礎控除額の差し引き算出
遺産総額が基礎控除額を超過しているケースでは、基礎控除額の超過分に相続税がかかります。「課税遺産総額」は、下記の公式で求められます。
「課税遺産総額=遺産総額−基礎控除額」
遺産総額とは「不動産」「預貯金」「株式」「みなし相続財産(受納予定の生命保険金と死亡退職金)」「相続開始前3年間の贈与財産」を足した金額から、負債や葬儀にかかった費用を引いた金額です。遺産総額が間違っていると、相続金額や相続税の算出にも影響を及ぼすため、すべての財産を確実に把握しておいた方がよいでしょう。
遺産総額が6,000万円、法定相続人が配偶者と子供二人であるケースでは、前述した基礎控除額の4,800万円をもとに算出できます。減算した課税額は「課税遺産総額=6,000万円−4,800万円=1,200万円」です。
「相続開始前3年間の贈与財産」に関しては、令和5年度税制改正によって相続開始前の「3年」の間の贈与に関して相続財産に加算されていたものが「7年」に延長されます。2024年の贈与から適用されますが、特別措置として、相続開始前の4年〜7年以内に贈与によって取得した財産の合計から100万円を控除した残額が相続税の対象となります。

株式を相続する方法や税金の計算方法を解説!非上場株式との違いとは

「みなし相続財産」とは?非課税枠や注意点をわかりやすく解説!

暦年贈与とは?連年贈与や名義預金とみなされない工夫で完璧な相続税対策を
3.課税対象額の算出
| 相続人 | 法定相続分 |
|---|---|
| 配偶者のみ | 配偶者が100% |
| 子がいる配偶者 | 配偶者が2分の1 子供が2分の1(人数で等分) |
| 子のみ | 子が100% |
| 配偶者と直系尊属(父母等) | 配偶者が3分の2 直系尊属(父母等)が3分の1(人数で等分) |
| 直系尊属(父母等)のみ | 直系尊属(父母等)が100% |
| 配偶者と兄弟姉妹 | 配偶者が4分の3 兄弟姉妹が4分の1(人数で等分) |
| 兄弟姉妹のみ | 兄弟姉妹が100% |
遺贈を考慮せずに、課税遺産総額を法定相続人のみで分割すると仮定し、各法定相続人に配分される相続税額を算出します。法定相続分の配分割合と、相続税の税率および控除額は、下記の公式で導き出せます。各人に課税遺産額の割合分を割り振り、税額の算出後に、すべての税額を足したものが「相続税額の合計」です。
「相続税額の合計=配偶者の相続税額+子供の相続税額+父母や兄弟姉妹の相続税額」
法定相続人が配偶者と子供二人、課税遺産総額が4,000万円の例を挙げると、相続人の負担割合から「配偶者:4,000万円×1/2=2,000万円」「子供(一人につき):4,000万円×1/4=1,000万円」に分割します。
さらに、各人の課税遺産額に相続税率をかけて控除額を引き、仮の相続税額を算出すると「配偶者:2,000万円×15%−50万円=250万円」「子供(一人につき):1,000万円×10%−0万円=100万円」です。これにより「相続税額の合計=250万円+100万円+100万円=450万円」と求められます。ただし、この「相続税額の合計」は「仮」の税額であるため、相続税額はまだ確定していません。
4.相続人各人の相続税額の算出
法定相続人各人の相続税額から、相続税額の合計を算出した後は、これをもとに、受け手に対する各人の相続税額を改めて算出します。受け手には、遺贈を受納する第三者まで含めましょう。受け手各人の相続財産を受納する割合を算出し、相続税額の負担割合と等しくなるよう設定すると、各人の相続税額を導き出せます。
「相続人各人の相続税額=相続税額の合計×(相続人各人の課税相続価額÷遺産総額)」
例として、遺産総額が8,800万円、課税遺産総額が4,000万円、法定相続人は配偶者と子供二人、第三者へ800万円の遺贈があるケースでは、4人の割合として第三者が800万円、配偶者が8,000万円の1/2(4,000万円)、子供が1/4ずつ(2,000万円)です。
相続税額合計の450万円をもとに、各人の負担割合は「配偶者:450万円×(4,000万円/8,800万円)=204.54万円」「子供(一人につき):450万円×(2,000万円/8,800万円)=102.27万円」「第三者450万円×(800万円/8,800万円)=40.9万円」と算出できます。ただし、第三者の相続税の算出はまだ終了していません。
5.税額軽減措置として各種の控除
各人の相続税額には、税額軽減措置として、各種税額控除額の適用が可能です。相続税の税額控除には「配偶者の税額軽減」「外国税額控除」「贈与税額控除」「障害者控除」「未成年者控除」「相次相続控除」があるため、当てはまる控除額により相続税が軽減されます。
配偶者の場合は、遺産の1億6,000万円まで、もしくは法定相続分の金額までであれば、相続税が課されません。ただし、相続人以外の者が遺贈を受納するケースにおいて、障害者控除、未成年者控除、相次相続控除は対象外です。

相続税の配偶者控除とは?適用条件や申告方法、注意事項を徹底解説

外国税額控除とは?計算方法と確定申告について解説!二重課税を防ぐために!
6. 法定相続人以外の第三者の相続税
法定相続人以外の第三者の相続税には、法定相続人が課せられる相続税額に比べて2割分が加算されます。
相続人各人の相続税額を算出した後に、その税額に2割分を加算します。上記の例を挙げると「第三者:450万円×(800万円/8,800万円)=40.9万円」に、2割増の相続税額を当てはめて「40.9万円×1.2=49.08万円」と導き出せます。

相続税の計算方法をわかりやすく解説!早見表から控除を踏まえた事例も紹介
遺贈を相続する時の注意点

遺贈には「相続税の2割分が加算される」「第三者には基礎控除が使えない」「死亡退職金・死亡保険金に非課税枠がない」「不動産取得税がかかる」など、税金面における注意点があります。
相続税の2割分が加算される
法定相続人である配偶者・子供・父母、もしくは代襲相続人の遺贈の場合、通常の相続税額の支払いで済みます。しかし、代襲相続人ではない孫・兄弟姉妹・甥・姪、これまでにお世話になった者など、法定相続人以外の第三者が遺贈を受納した場合は、相続税に2割分が加算されます。遺贈を検討している場合には、受遺者に増額された相続税を支払う義務がある点に注意しましょう。
第三者は基礎控除額の算出に入らない
相続税の基礎控除額は、法定相続人の数によって変動するため、相続財産を受納する者の数は基礎控除の算出に関係ありません。遺贈によって相続財産を受納する者が増えても、相続税の基礎控除額は変わらないので、法定相続人の数に遺贈者を含めないよう注意しましょう。
死亡退職金・死亡保険金は非課税枠がない
第三者が遺贈された場合、死亡退職金・死亡保険金には相続税の非課税枠が設けられていません。これらの財産はみなし相続財産と呼ばれ、相続時には相続対象の財産であると判断され、相続税の非課税枠が存在します。
非課税枠の公式は「非課税限度額=500万円×法定相続人の数」です。ただし、第三者が死亡退職金・保険金を受納した場合は、この非課税枠が応用されない点を把握しておきましょう。

生命保険は相続税・贈与税・所得税がかかる?契約内容による違いを解説
不動産取得税と登録免許税がかかる
法定相続人以外の第三者への特定遺贈によって、特定の土地や建物が遺贈されるケースでは、不動産取得税の納付義務が課せられています。一方で、財産を割合のみを限定した包括遺贈や、法定相続人が受遺者になる場合には納付が不要です。
不動産を受納した後に名義を変更するのに、登録免許税もかかります。登録免許税は、相続人が受遺者のケースでは0.4%ですが、第三者が遺贈で受納したケースでは2%と、通常の5倍の金額です。例えば、固定資産税評価額が1,000万円として、0.4%は4万円ですが、2%は20万円と、高額になってしまいます。

相続した土地の売却にかかる税金はいくら?税金の計算方法や相続税対策
まとめ

「遺贈(いぞう)」とは、遺言に従って相続財産を相続人、あるいは第三者の個人や法人などに、無償で譲渡することです。兄弟姉妹や子供、孫などの親族、介護や身の回りの世話をしてくれたお嫁さんに少しでも財産を譲りたいと思う人もいるでしょう。ですが、財産の相続には税金がかかり、その納税額によってはかえって負担となってしまう場合があります。遺贈と相続税について理解を深め、感謝の気持ちが裏目に出ないよう、負担にならない形で贈れるよう準備したいですね。
ご留意事項
- 本稿に掲載の情報は、ライフプランや資産形成等に関する情報提供を目的としたものであり、特定の金融商品の取得・勧誘を目的としたものではありません。
- 本稿に掲載の情報は、執筆者の個人的見解であり、三菱UFJ信託銀行の見解を示すものではありません。
- 本稿に掲載の情報は執筆時点のものです。また、本稿は執筆者が各種の信頼できると考えられる情報源から作成しておりますが、その正確性・完全性について執筆者及び三菱UFJ信託銀行が保証するものではありません。
- 本稿に掲載の情報を利用したことにより発生するいかなる費用または損害等について、三菱UFJ信託銀行は一切責任を負いません。
- 本稿に掲載の情報に関するご質問には執筆者及び三菱UFJ信託銀行はお答えできませんので、あらかじめご了承ください。