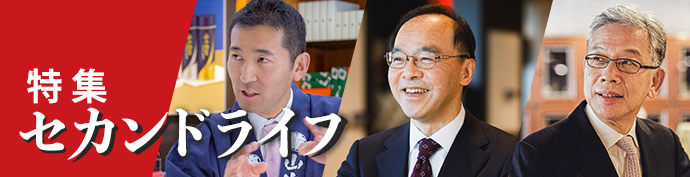生命保険は相続税・贈与税・所得税がかかる?契約内容による違いを解説
生命保険に加入していた被保険者が亡くなって支払われる死亡保険金は、受取人によって、相続税、所得税、贈与税というように課税される税金が変わってきます。今回は、誰が受け取ればどのような税金がかかるかを解説します。相続税の控除や生命保険の活用方法も参考にしてみてください。

生命保険で受け取るお金にかかる税金

生命保険の保険金(死亡保険金や満期保険金)は、契約者・被保険者・受取人の組み合わせに応じて、相続税・所得税・贈与税のいずれかが課されます。ただし、保険金の支給額や保険金の種類によっては、税金がかからないこともあります。
そこでまずは、生命保険の保険金はどのような税金が課されるのか、また、税金が課されない場合とはどのようなケースなのかを解説します。
生命保険金に相続税がかかる場合
生命保険の保険料を被相続人が支払っていた場合、保険金の受取人には相続税がかかります。しかし、死亡保険金については、常に相続税がかかるというわけではなく、基礎控除枠や非課税枠があります。
相続税は、相続した遺産が一定額を超える場合にかかる税金です。具体的には、課税対象となる遺産が「600万円×法定相続人の人数に3,000万円を足し合わせた額」(基礎控除額)を超えた場合に限り、相続税が課されます。例えば法定相続人が1名の場合の基礎控除額は、600万円×1+3,000万円=3,600万円です。
さらに、死亡保険金にはこの基礎控除とは別に非課税枠があります。そのため「500万円×法定相続人の人数」までは相続税が課せられません。

相続税の計算方法をわかりやすく解説!早見表から控除を踏まえた事例も紹介
生命保険金に所得税がかかる場合
生命保険の保険料を受取人が支払っていた場合、被保険者の死による死亡保険金に対しては所得税がかかります。
例えば、父親が生命保険の被保険者、子供が生命保険の契約者兼受取人という場合です。この時、生命保険の支給額は一時所得として扱われ、一定の控除などを受けたうえで所得税が課税されます。
生命保険金に贈与税がかかる場合
生命保険が「生前贈与」扱いになって、贈与税が課せられる場合もあります。
例えば、母親が契約者(保険料の負担者)、父親が生命保険の被保険者、子供が保険金の受取人というケースです。この場合、保険金の支給は税務的には、母親から子供に対しての生前贈与であるとみなされるため、子供が受け取る保険金には贈与税がかかります。

「生前贈与」とは?活用すべき人や贈与の方法、メリット・デメリットを徹底解説
生命保険金に税金がかからない場合もある
生命保険契約によって支払われる保険金のなかには、税金がかからないものもあります。それは入院給付金や手術給付金、高度障害保険金など、被保険者自身の疾病や障害などを理由に支払われる保険金です。これらは税法上で非課税とすることが定められています。
生命保険の相続には非課税枠がある

生命保険の相続には、非課税枠が設けられています。この非課税枠の上限は、法定相続人の人数に応じて、以下の計算式で示されます。
生命保険の非課税枠=500万円×法定相続人の人数
この法定相続人とは、民法で定められた相続人です。たとえ相続人のなかの誰かが相続放棄の手続きをした場合も、上記の計算式の法定相続人の人数は変わりません。このとおり生命保険の保険金の課税額には非課税枠が設けられているため、相続税負担を減らす手段として生命保険が活用されることもあります。

法定相続人はどんな順位できまる?遺産の取り分や例外での注意点を解説
非課税枠のない生命保険もある
生命保険の中には、上記の非課税枠が使えない場合もあるので注意が必要です。すでに紹介したように生命保険に課される税金の種類は、契約者(保険料の負担者)・被保険者・受取人の組み合わせによって変わり、所得税や贈与税を課せられる場合もあります。そして、思い出していただきたいのは、先に紹介した非課税枠とは「相続税」の計算における非課税枠であるということです。
例えば、子供が契約者(保険料の負担者)兼受取人で、父親が被保険者の時に支給される生命保険には「所得税」が課されます。そして、この所得税には相続税の非課税枠は使えません。これは母親が契約者(保険料の負担者)で父親が被保険者、子供が受取人で贈与税扱いになる場合も同様です。
死亡保険金の被保険者・受け取る人の違い

次の表は、保険金の種類ごとに、契約条件に応じて受け取り時にかかる税金を一覧化したものです。
死亡保険金の場合
| 契約条件 | かかる税金 |
|---|---|
| 契約者=被保険者 | 相続税 |
| 契約者=受取人 | 所得税 |
| 契約者、被保険者、受取人が全て別人 | 贈与税 |
満期保険金の場合
| 契約条件 | かかる税金 |
|---|---|
| 契約者=受取人 | 所得税 |
| 受取人が契約者以外 | 贈与税 |
ここまで解説してきたことからもわかるように、死亡保険金に対してどのような税金が課されるかは、生命保険の契約者(保険料の負担者)、被保険者や受取人などがどのように設定されているかで変わってきます。以下ではあらためて、その違いについて解説します。
契約者と被保険者が同じ場合
生命保険の契約者(保険料の負担者)と被保険者が同一人物であるケースでは、支給された死亡保険金は相続税の課税対象になります。相続人が受け取った死亡保険金には「500万円×法定相続人の人数」の非課税枠が設けられているため、相続税の負担を少なくするためにはこの形が最も効果的です。
契約者と保険金受取人が同じ場合
生命保険の契約者(保険料の負担者)と受取人が同じケースでは、支給された保険金は所得税の課税対象になります。保険料を負担している当人が保険金を受け取るので、所得の一種として捉えられる形です。この場合、所得税法上は一時所得として取り扱われますが、課税対象となる一時所得の金額は以下の計算式で算出されます。
課税所得額=(保険金支給額-これまで支払ってきた保険料-特別控除50万円)×1/2
契約者、被保険者、保険金受取人それぞれが別人の場合
生命保険の契約者(保険料の負担者)、被保険者、受取人がすべて別人の場合に支払われた保険金は贈与税の対象となります。これは契約者が支払ってきた保険料によって発生した利益(保険金)が、契約者の存命中に受取人へ贈与されたとみなされるためです。なお、贈与税には年間110万円までの基礎控除額が設置されているため、支給された保険金から110万円を差し引いた額が課税対象になります。
相続税の控除

相続税に対しては、基礎控除のほかにも相続人の属性や相続時の状況などに応じたさまざまな控除制度が設けられています。支給された保険金を含む相続財産が基礎控除額より少なかったり、相続人が負担する相続税額がこれらの控除額よりも少なければ、相続税を支払う必要はありません。以下では、相続税の控除制度の一覧とその控除内容を簡単に紹介します。
基礎控除額
基礎控除は、相続を受ける人ならば誰でも受けられる控除です。基礎控除は以下の計算式によって算出されます。
基礎控除額=3,000万円+(600万円×法定相続人の人数)
つまり、法定相続人が一人のみの場合でも、最低限3,600万円分の控除を受けられるということです。そして、法定相続人の人数が増えるに応じて、600万円ずつ控除額は高くなっていきます。相続財産が控除額以下であれば、相続税の納税義務は生じず、申告の必要もありません。

相続税の基礎控除とは?計算方法や知っておくべき法定相続人を解説
債務控除
債務控除とは、被相続人が未納していた税金や借入金などの債務額分を遺産総額から差し引けるという控除です。また、債務とはいえませんが、被相続人のお葬式にかかった費用なども遺産総額から差し引くことが認められています。なお、相続人の責任によって生じた延滞税や加算税などは債務控除の対象にならないのでご注意ください。
配偶者の税額軽減
配偶者の税額軽減とは、被相続人の配偶者に対して設けられている税額の軽減措置です。配偶者の税額軽減においては、配偶者の法定相続分または1億6,000万円のうち、いずれか大きい金額まで相続税が控除されます。
例えば、配偶者の法定相続分が50%で、遺産総額が5億円だった場合は、配偶者が取得した財産が2億5,000万円までは相続税が課税されません。ほかの相続税の控除と比べても、配偶者の税額軽減は優遇されていますが、それは配偶者の生活保障という点と、被相続人の資産形成において配偶者が果たしたであろう貢献度に着目してこのように設定されています。
なお、配偶者の税額軽減を受けられるのは、法的な手続きを経て婚姻した者だけなので、内縁の妻などは配偶者の税額軽減を受けることができません。

相続税の配偶者控除とは?適用条件や申告方法、注意事項を徹底解説
未成年者控除
未成年者控除とは、相続人が未成年であった場合に適用される控除です。被相続人の命日に未成年であった日本在住の人がこの控除の対象になります。控除額の計算方法は以下のとおりです。
10万円×その未成年者が成人するまでの年数
未成年者の場合、成人するまでは養育費などが必要になるという観点からこの控除が設けられています。なお、未成年の定義は以前までは20歳未満でしたが、民法の改正により2022年4月以降は18歳未満に変更されました。
障害者控除
障害者控除とは、相続人のなかに障害者が存在する場合に適用される控除です。障害者は通常よりも多くの生活費や療養費、医療費などを要することから、該当する相続人の生活を保障するためにこの制度が設けられています。障害者控除の適用対象となるのは、被相続人の亡くなった日に85歳未満である障害者です。障害者控除の控除額は、障害の区分(一般障がい者・特別障がい者)、相続人の年齢などによって変化します。
障害者控除を受けるには基本的に身体障害者手帳などの交付を受けている人が対象になりますが、相続税の申告書を提出するまでに障害者手帳の交付を受けた人や、一定の要件を満たした交付申請中の人ならば、控除の適用を受けることが可能です。
贈与税額控除

贈与税額控除とは、被相続人が亡くなった日から3年以内に受けた生前贈与について贈与税を納税していた相続人が受けられる控除です。そこで支払った贈与税分を今回の相続税から差し引くことができます。これは相続法においては、亡くなる3年以内に受けた生前贈与は相続税の課税対象になるという制度の影響を受けて設けられています。
相続税の持ち戻しの対象期間は、令和5年の暦年贈与制度の改正によって3年から7年へと変更されます。令和6年1月1日以後の贈与から適用され、令和8年(2026年)12月より前に相続が開始した場合は、これまでの暦年贈与制度の持ち戻し期間と同様に期間は3年となります。令和9年(2027年)1月からは、相続税の持ち戻し期間が加算されていき、令和13年(2031年)からは持ち戻しの期間は、7年間となります。
つまり、すでに贈与税を支払っているにもかかわらず、同じ資産にさらに相続税を課すのは二重課税になるため、それを防ぐための法律です。なお、亡くなる3年以内に生前贈与を受けていた場合でも、その贈与が贈与税の基礎控除額以下で税金を払っていなかった場合は、贈与税額控除の適用対象にはなりません。

【税制改正対応】贈与税申告が必要なのはどんなとき?申告手順も解説
相次相続控除
相次相続控除(そうじそうぞくこうじょ)とは、一次相続と二次相続が10年以内に相次いで発生した場合に適用される控除です。両親のうち片方が亡くなった際に生じる相続が一次相続、その後、残された親が亡くなった際に生じる相続が二次相続と呼ばれています。
相次相続控除の控除内容は、一次相続の際に納税した相続税の一定額を、二次相続の際の相続税から差し引けるというものです。この控除は短い期間に同一の資産に対して続けざまに相続税を課すのは二重課税に当たるため、それを防ぐために設けられています。
相次相続控除の控除額は、一次相続から二次相続までの経過期間に応じて10%ずつ減額されます。逆にいえば、一次相続から二次相続までの期間が近いほど多くの控除が適用されるということです。

二次相続とは?相続税の負担を減らす相続配分や控除活用のコツを解説
【メリット】生命保険の上手な活用方法

最後に、遺産相続において生命保険を活用するメリットや、上手な活用方法について紹介します。
余裕資金がある場合は一時払い終身保険
まずは生命保険を活用して相続税の負担を少なくする方法からお伝えしていきましょう。生命保険に未加入の方で、資金に余裕がある場合は、「一時払い終身保険」という生命保険に加入するのが相続税の負担を少なくする方法として有効です。
一時払い終身保険とは、保険加入時に一括で保険料を支払っておくことで、被保険者が亡くなった際には、支払った保険料と同額の保険金の支給を受けられるという保険商品です。「終身保険」とあるように、保険料を支払った後なら、いつ亡くなったとしても死亡保障は履行されます。
これは一見すると、放出した手元資金が亡くなった後に戻ってくるだけに思えるかもしれませんが、相続税の負担を少なくすることにつながります。資産を預貯金のまま保有していた場合、亡くなった時には預貯金全体が相続税の対象になってしまいます。しかし生命保険の保険料としていったん消費しておけば、その分だけ課税対象となる預貯金を減らすことができ、さらに相続の際に生命保険の非課税枠を利用できるようになります。
例えば、8,000万円の資産総額があり、法定相続人が4人いる場合を考えてみましょう。この場合、一時払い終身保険の保険料として2,000万円(非課税枠の上限)を支払っておけば、課税対象となる資産を6,000万円に減らしつつ、2,000万円分の資産を税金が取られない形で保存しておけます。法定相続人が4人いる場合、相続税の基礎控除は「3,000万円+(600万円×4人)」で5,400万円になるので、600万円分の課税財産に対して相続税を支払うのみになります。逆に預貯金のまま資産を保有していた場合は、2,600万円の課税財産に対して相続税が課税される計算です。
孫や子供に生命保険をかける

孫や子供に生命保険をかけるのも有効な手法です。これは生命保険の「解約返戻金」の仕組みを利用しています。解約返戻金とは、保険を解約した際に戻ってくるお金のことで、相続税の評価額にもなります。解約返戻金は支払った保険料や加入期間に応じて増えていくのが通例ですが、この仕組みが相続税の負担を少なくすることにつながります。
例えば、10年目以降に解約返戻金の額が大きく上がる保険に孫や子供を加入させたらどうでしょう。9年目にその保険を孫や子供に相続させたとしても、解約返戻金はまだ少額のため、ほとんど相続税はかかりません。そして、孫や子供は相続してから1年分の保険料を支払うだけで、10年目以降に多額の解約返戻金を受け取ることができます。
保険金を一時所得で受け取る
生命保険の非課税枠を使い切っている場合は、それを超過する分を一時所得の形で受け取るように計画するのも一考の価値があります。基本的に生命保険を受け取る場合は、非課税枠を使える分、相続財産の形にしておくのが得策です。
しかし、この非課税枠を使っても多額の資産が残るような場合は、相続税よりもむしろ所得税の形で課税された方が、税額が安くなる場合があります。というのも、生命保険を一時所得として扱う場合は、「(保険金支給額-これまで支払ってきた保険料-特別控除50万円)×1/2×税率」というように、受け取った保険金額の1/2以下の価額に対して所得税率をかけることになるためです。
したがって、非課税枠を差し引いた保険金額にかかる相続税率が所得税率とそう変わらない場合は、課税対象額に1/2を乗算する一時所得扱いのほうが税負担は低くなります。
保険金を一時所得として受け取るためには、被保険者(被相続人)の保険料を受取人が支払い続けなければいけません。しかし、その資金についても生前贈与などを活用することで、受取人の支払い負担を減らせるでしょう。
遺産分割協議をしなくて大丈夫
契約者と被保険者が同一人物である生命保険の保険金は、民法上で受取人固有の資産という扱いになるため、原則的に遺産分割協議で話し合うべき協議対象に含めなくてよいのもメリットです。
例えば、法定相続人以外で生前にお世話になった人に特別に資産を遺したいなどの希望があれば、その人を生命保険の受取人に指定しておくことで、保険金額の全額を渡すことができます。遺産分割協議においては、相続人のあいだで争いが生じることもありますが、そうしたトラブルからも距離を置いて相続させることが可能です。

「遺産分割協議」とは?遺産分割協議書の書き方や手続きの注意点を解説
相続放棄をしても受け取ることができる
受取人固有の資産として扱われるという特性により、生命保険は相続放棄した人でも受け取れるという利点があります。遺産相続において相続人が引き継ぐのは、プラスの資産だけとは限りません。もしも被相続人が多額の債務を残していた場合、マイナスの資産も相続する義務があります。
相続によって利益よりも不利益が多く見込まれる時に行われるのが相続放棄です。通常、相続放棄を行った場合は相続人としての全ての相続の権利も義務も失うことになります。しかし、生命保険については別です。生命保険は受取人の資産として法律上捉えられるので、相続放棄をしても受け取ることができます。
ただし、受け取った保険金は相続税の課税対象であり、相続放棄をした場合は生命保険の非課税枠を利用できなくなってしまうので、その点は注意が必要です。その他の相続関係の控除も使えなくなるため、相続放棄をする際はメリットとデメリットを慎重に考えましょう。

相続放棄とは?遺産の価値や限定承認も検討して放棄すべきか考えよう
遺留分の対象外
生命保険は原則的に遺留分の対象外であることもメリットです。遺留分とは、法定相続人が最低限取得する権利があると法律で定められた遺産の取り分です。通常、遺産相続においては被相続人の意思が最大限尊重されますが、遺留分に関しては被相続人であっても侵害することはできません。したがって、たとえ被相続人が遺産を相続させたくないと思う相手でも、遺留分については相続を認めざるをえません。
しかし、そこで役に立つのが生命保険です。生命保険は基本的に遺留分の対象外のため、特定の相続人に多くの財産を相続させたいという場合は、生命保険の受取人をその相手にすることで、被相続人の望みを叶えることができるでしょう。
ただし、例外的な事例として、あまりにも遺産全体の総額と生命保険金額が不釣り合いな場合は、生命保険も遺留分に含まれる可能性があります。例えば相続財産が100万円なのに対して、生命保険金額が5,000万円あるという場合は、相続人のあいだに著しい不公平が生じます。ケースバイケースなところもありますが、生命保険金が遺留分に含まれる場合もあるため、遺産配分が極端にならないように気をつけてください。

遺留分とは?相続できる内容や侵害された時の請求の手続きを学ぼう
まとめ
生命保険にかかる税金は、契約者・被保険者・受取人が誰かによって変わります。生命保険をどのような形で契約するかは、相続税の課税額に大きくかかわる重要な問題です。将来、最良の方法でお金をご家族に残したい方は、生命保険の知識を深めるようにしましょう。
ご留意事項
- 本稿に掲載の情報は、ライフプランや資産形成等に関する情報提供を目的としたものであり、特定の金融商品の取得・勧誘を目的としたものではありません。
- 本稿に掲載の情報は、執筆者の個人的見解であり、三菱UFJ信託銀行の見解を示すものではありません。
- 本稿に掲載の情報は執筆時点のものです。また、本稿は執筆者が各種の信頼できると考えられる情報源から作成しておりますが、その正確性・完全性について執筆者及び三菱UFJ信託銀行が保証するものではありません。
- 本稿に掲載の情報を利用したことにより発生するいかなる費用または損害等について、三菱UFJ信託銀行は一切責任を負いません。
- 本稿に掲載の情報に関するご質問には執筆者及び三菱UFJ信託銀行はお答えできませんので、あらかじめご了承ください。