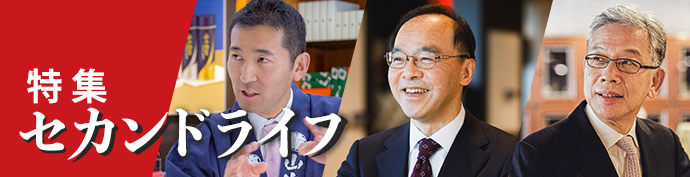「生前贈与」とは?活用すべき人や贈与の方法、メリット・デメリットを徹底解説
生前贈与とは生前に本人の意思で、他人に財産を譲ることです。この記事では、生前贈与財産の仕組みやメリット・デメリット、税負担を軽減する上での注意点を解説します。生前贈与をはじめ、さまざまな制度を活用して自身の財産や死後の相続について考えましょう。

生前贈与とは?

生前贈与とは、自身の財産を存命中に他人に贈与することです。財産を渡す側を「贈与者」といい、受け取る側を「受贈者」といいます。生前贈与が認められると一定額までの贈与税は非課税となります。生前贈与を活用して自身の財産を減らすことができれば、相続する遺産が少なくなるので相続税の負担を軽減できます。
生前贈与には、「暦年課税」と「相続時精算課税」の2種類があり、どちらの方式を選択するのかによって非課税の対象となる控除額が変わります。
相続と贈与の違い
相続は、亡くなった方の財産や財産に関わる権利義務を相続人に受け継ぐことを指します。生前贈与は財産を所有している方が生きているうちにおこなわれるのに対し、相続は亡くなった後に発生するものです。生前贈与は財産を受け渡す意思があることでおこなわれますが、相続は財産を所有している方が亡くなった場合に自分の意思とは関係なく発生するという違いもあります。
財産を所有している人が生きているうちに相続に関する取り決めをおこなうことも可能ですが、急逝することも考えられます。この場合、想定外の相続が発生するため、財産の分配割合や方法をめぐって相続人のあいだでトラブルに発展するケースもあります。こうしたトラブルを防ぐためにも、生きているうちに財産を贈与する生前贈与は効果的です。
暦年課税とは
暦年課税は、受遺者が1月1日~12月31日までの1年間に受け取った財産の金額が110万円を超えた場合に、超過した金額に対して贈与税がかかる制度です。受贈者が相続時精算課税を選択しなかった場合に暦年課税となります。
暦年贈与は、贈与者が死亡する前3年以内に相続人が贈与を受けていた場合、その贈与分は被相続人の相続財産として加算されます。またこの3年という期間は、2023年(令和5年)12月31日までの相続が対象です。
2023年度(令和5年度)税制改正大綱により、生前贈与加算の対象期間が3年から7年に延長されることが決定しました。2024年(令和6年)1月1日以後に贈与により取得する財産に係る相続税から適用されます。

暦年贈与とは?連年贈与や名義預金とみなされない工夫で完璧な相続税対策を
相続時精算課税とは
相続時精算課税は、60歳以上の父母や祖父母等が18歳以上の子供や孫等に贈与する場合に、2,500万円まで贈与税がかからない制度です。
贈与者が逝去した場合には、贈与された財産を相続財産に加算して相続税を計算します。そのため、課税の先送りにすぎないと捉えることもでき、税負担の軽減はほとんど望めません。ただし、財産の時価が相続までに上がった場合でも贈与時の時価に対して相続税がかかるため、確実に時価が上がる財産を贈与するなら税負担を軽減できるでしょう。
なお、2023年度(令和5年度)税制改正大綱により、相続時精算課税制度の特別控除2,500万円に、年110万円の基礎控除枠が追加されることになりました。2024年1月1日以後に贈与によって取得する財産について適用されます。
【参照】財務省「令和5年度税制改正の大綱(2/10)」詳しくはこちら

相続時精算課税制度とは?手続き方法やメリット・デメリットを解説
生前贈与のメリット

生前贈与を利用することで、いくつかのメリットが発生します。ここではその中から3つのポイントをご紹介します。
暦年課税なら毎年累積できる
暦年課税で生前贈与をおこなう場合は110万円が基礎控除額となり、1年間に受け取る贈与額が110万円を超えなければ贈与税がかかりません。110万円は1年間の総額なので金額としては少ないと考える方がいるかもしれませんが、毎年110万円ずつ贈与すれば累積の効果で金額を大きくできます。
ただ毎年一定額を贈与すると定期贈与とみなされて、贈与税を課税される可能性があるので注意しましょう。定期贈与に関しては、後述するので参考にしてみてください。
相続税の負担を軽減できる
相続税にも基礎控除があり、以下の計算式で求めた基礎控除額を超えた分にのみ相続税が発生します。
■3,000万円+(600万円×法定相続人の数)
例えば法定相続人が二人の場合は「3,000万円+(600万円×2)」となるので4,200万円が基礎控除額です。相続する遺産の総額が4,500万円だった場合は「4,500万円-4,200万円」となり、300万円に対して相続税が発生します。
このケースで過去に310万円の生前贈与をおこなっていた場合は、相続時の遺産が4,190万円となるため基礎控除額を下回り相続税が発生しません。このようにあらかじめ生前贈与をしておくことで、後々に発生する相続税の負担を軽減することが可能です。
贈与者が決めた相手に贈与できる
相続では、財産を取得できる人は法律で決められているため、遺言書がなければ財産を渡す相手を自由に決めることはできません。遺言書があれば故人の意思で財産を分けることが可能ですが、急逝した場合には遺言書を残していないことも考えられます。
一方、生前贈与では、贈与者が決めた相手に財産を渡せます。存命のうちであれば、親族が納得できない相手でも説得できる可能性があるでしょう。

遺言書の種類一覧と作成方法!種類別のメリットとデメリットも解説
生前贈与のデメリット

生前贈与にはデメリットも存在します。贈与を考えている方は、メリットとデメリットを天秤にかけて実施しなければいけません。
定期贈与とみなされると贈与税がかかる
定期贈与は、まとまった金額を分割して毎年一定の金額を贈与する方法です。定期贈与とみなされると、贈与の総額に対して贈与税がかかってしまう場合があります。例えば、毎年110万円を5年間贈与して定期贈与とみなされた場合は、550万円に対して贈与税がかかります。
特に贈与者と受贈者のあいだで「毎年一定の金額を贈与する」という取り決めがおこなわれた場合は、取り決めた年に「定期金に関する権利」の贈与を受けたものとして贈与税がかかるため注意が必要です。

定期贈与とは?連年贈与との違いや定期贈与とみなされないためのポイント
死亡前3年以内の贈与は相続税がかかる(※7年に延長あり)
被相続人が亡くなった日前3年以内に暦年贈与によって贈与した財産があった場合は、贈与した金額が相続財産に加算されます。相続税の負担を軽減させるための贈与でなくても、3年以内に亡くなってしまった場合はその贈与金額が相続税の対象になるので注意が必要です。
またこの3年という期間が適用されるのは、2023年12月31日までに発生した相続が対象です。令和5年度(2023年)税制改正大綱が発表され、生前贈与加算の対象期間が3年から7年に延長されることが決定しました。2024年(令和6年)1月1日以後の贈与により取得する財産に係る相続税について適用されます。
例えば自分に病気等が判明して、急いで贈与を考える方もいるかもしれません。しかし、3年(2031年からは7年)が経過しないうちに亡くなってしまうと相続税がかかるので、このケースでは生前贈与による相続税の負担軽減は難しくなります。生前贈与は駆け込み的におこなうのではなく、できるだけ早めに始めることが大切です。
【参照】総務省「令和5年度税制改正の大綱(PDF)」詳しくはこちら
名義預金とみなされると課税対象になる
名義預金とは、贈与者が受贈者の名義で口座を作成して、財産を残すことをいいます。受贈者が口座の存在を知らなかったり、自分で口座を管理していなかったりすると、名義預金とみなされます。名義預金によって残された財産は相続税の対象となるため、贈与のつもりで残していた場合も課税される恐れがあります。
よくあるのが配偶者や子供、孫のために銀行口座を作成して、自身の財産を入れておくケースです。生前贈与では、贈与者と受贈者が受け取りを認識する必要があるため、この場合は名義預金とみなされます。

名義預金とは?判定基準や贈与税・相続税がかかる際の注意点を解説
高額の贈与には向かない
生前贈与は高額の贈与には向かない場合があります。特に不動産は高額になることが多く、贈与税もその分多くかかります。また不動産を取得する場合には登録免許税が発生し、税率は相続よりも贈与のほうが高く設定されています。さらに贈与では不動産取得税も発生します。
もっとも、生前贈与と相続のどちらの方が税負担が軽減できるかはケースバイケースです。迷った場合は専門家へ相談するのがよいでしょう。

土地の相続税はいくら?評価や計算方法、相続税の軽減方法について解説

相続の相談は誰にする?弁護士、税理士、司法書士、信託銀行で比較!
贈与税の計算方法

暦年課税の場合は、贈与額から基礎控除の110万円を差し引いた金額(課税価格)に税率をかけ、さらに控除額を差し引いて計算します。
■暦年課税における贈与税の計算式:(贈与額-110万円)×税率-控除額
暦年課税は贈与の額によって税率と控除額が決まる仕組みです。税率と控除額は一般贈与財産用(一般税率)と特例贈与財産用(特例税率)の2つがあります。
一般税率は、直系尊属以外からの贈与や直系尊属から未成年への贈与の場合に適用されます。例えば、直系尊属ではない夫婦や兄弟からの贈与、父母や祖父母から未成年者への贈与が一般税率で計算されます。
特例税率は、直系尊属から成人者への贈与で適用されます。父母や祖父母から成人した子供、孫への贈与等がこれに当たります。注意したいのが成人年齢です。成人年齢は2022年4月1日に18歳に引き下げられました。そのため、2022年3月31日以前の贈与は20歳以上、4月1日以降の贈与では18歳以上が該当します。
一般税率
| 基礎控除後の課税価格 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 200万円以下 | 10% | - |
| 300万円以下 | 15% | 10万円 |
| 400万円以下 | 20% | 25万円 |
| 600万円以下 | 30% | 65万円 |
| 1,000万円以下 | 40% | 125万円 |
| 1,500万円以下 | 45% | 175万円 |
| 3,000万円以下 | 50% | 250万円 |
| 3,000万円超 | 55% | 400万円 |
特別税率
| 基礎控除後の課税価格 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 200万円以下 | 10% | - |
| 400万円以下 | 15% | 10万円 |
| 600万円以下 | 20% | 30万円 |
| 1,000万円以下 | 30% | 90万円 |
| 1,500万円以下 | 40% | 190万円 |
| 3,000万円以下 | 45% | 265万円 |
| 4,500万円以下 | 50% | 415万円 |
| 4,500万円超 | 55% | 640万円 |
相続時精算課税の場合は、贈与額から特別控除の2,500万円を差し引いた金額に、税率20%(一律)をかけて計算します。
■相続時精算課税における贈与税の計算式:(贈与額-2,500万円)×20%
なお、2,500万円は複数年の累積限度額なので、前年以前に控除している場合は控除後の残額が限度額になります。
【参照】国税庁「No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)」詳しくはこちら
【参照】国税庁「No.4409 贈与税の計算(相続時精算課税の選択をした場合)」詳しくはこちら

贈与税は親子でも適応?課税方法や贈与税の対象にならない場合を解説
生前贈与をする際の注意点

生前贈与は注意点も多く、気をつけなければ税負担の軽減にならないばかりか、多額の税金がかかってしまう恐れもあります。以下で主な注意点を解説します。
受贈者との合意を確認する
贈与は、民法549条によって以下のように規定されています。
【参照】e-gov法令検索「民法」詳しくはこちら
条文から分かる通り贈与は、贈与者が財産を渡したいという意思だけでなく、受贈者が受け取ることを認識・承諾していなければいけません。例えば、相手に内緒で口座を作成して財産を残していた場合は、名義預金とみなされてしまい相続税がかかってしまいます。したがって、贈与する際には受遺者との合意を確認することが大切です。
贈与契約書の作成は必要
生前贈与は、諾成契約(だくせいけいやく)です。諾成契約とは、当事者間の合意のみで成立する契約を指し、口頭でも契約が成立します。そのため、贈与者と受贈者のあいだで口頭でも贈与の合意が成立した場合は契約書を作成する必要がありません。
しかし、贈与契約書は可能な限り、作成しておくことをおすすめします。口頭だけの約束の場合は、生前贈与の証拠が残りづらくなります。また、書面によらない贈与の当事者は履行前ならいつでも契約を撤回できるため、トラブルになる可能性もあります。
書面が残っていなければ、税務署から生前贈与と判断してもらえず、相続税が課せられる可能性もあります。こうした問題を避けるためにも、贈与契約書の作成が必要です。
不動産は名義変更登記が必要
不動産の贈与も口頭での合意だけで契約が成立します。しかし、登記簿に載っている名前が贈与者のままである場合、譲り受けたという証拠を第三者に示すことができません。名義変更をおこなったほうがトラブルを回避しやすくなります。
不動産の贈与契約書には、不動産の情報を入れておくことが大切です。登記事項証明書に記載の情報を正確に記載して、登記手続き費用や公租公課を誰が負担するか等も書面で決めておくと、後々の問題を避けられます。

【義務化】「相続登記」とは?不動産の相続に必要な手続きや費用について

家の名義変更は自分でできる?依頼した場合の費用や手続きの流れなどを解説
定期贈与とみなされないために対策をおこなう
暦年課税で贈与をおこなう場合は、定期贈与とみなされないように下記のような対策が必要です。
・贈与契約書を都度作成する
・贈与する金額を毎年変える
・贈与する時期を毎年変える
本当に贈与がおこなわれたことを示すために、贈与の都度、贈与契約書を作成するのが有効です。最初からまとまった金額を贈与するつもりではなかったことを示すために、贈与の時期や金額を毎年変えるのもポイントです。
暦年課税と相続時精算課税は併用できない
暦年課税と相続時精算課税制度は併用できません。また、暦年課税から相続時精算課税制度には変更できますが、その逆は不可能です。相続時精算課税制度を選択すると今後は暦年課税を使えなくなるため、よく考えて選択しなければなりません。
ただし、相続時精算課税は贈与者ごとに選択できます。例えば父と母のそれぞれから生前贈与を受ける場合、父からの贈与について相続時精算課税を選択し、母からの贈与は暦年課税とすることは可能です。
遺留分を侵害してしまう可能性も
一定の相続人については、遺産の最低限の取り分が法律で定められています。これを遺留分といいます。
特定の人に生前贈与をしたことで相続人の相続できる財産が遺留分を下回った場合には、当該相続人はその金額を取り戻すために遺留分侵害請求が可能です。贈与者が亡くなった後に、受贈者が親族から遺留分侵害請求を受けてトラブルとなるケースもあります。トラブルを避けるためには、生前贈与をする時に相続人の遺留分を侵害してないかを確認し、贈与の金額を決める必要があるでしょう。
そのほかにも活用したい贈与税の非課制度

財産の贈与では、ほかにも非課税となる制度がいくつかあります。さまざまな制度を活用することで税負担を軽減する効果を高められます。
教育資金の一括贈与
父母や祖父母といった直系尊属から30歳未満の子供や孫に対する教育資金の贈与は、1,500万円までが非課税となります。ここでいう教育資金とは、入学金、授業料、寮費、通学費、修学旅行代等、学校にまつわるものです。
一方、学校に関わらない教育資金(習い事や塾等)の場合は、受贈者が23歳未満に限り500万円までが非課税となります。
ただし、贈与者が亡くなった場合や、受贈者が30歳になった場合には、相続税や贈与税がかかる可能性があるので注意が必要です。
なお、この特例の適用期限は2023年3月31日まででしたが、2023年度(令和5年度)の税制改正大綱によると3年間延長される方針です。
【参照】国税庁「No.4510 直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税」詳しくはこちら
【参照】総務省「令和5年度税制改正の大綱(PDF)」詳しくはこちら

教育資金贈与の非課税制度の改正内容とは?特例の注意点もご紹介
住宅取得等資金贈与
住宅を新築・取得・増改築するのための資金を直系尊属から贈与された場合は、一定の贈与税が非課税となります。2022年1月1日〜2023年12月31日までの贈与に適用される制度で、非課税枠は省エネ等住宅で1,000万円、それ以外で500万円です。
住宅取得等資金贈与の制度を利用できる主な条件は、以下の通りです。
出典・贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与された住宅取得等資金の全額を住宅資金に充て、かつその住宅に居住すること
・受贈者は、贈与の年の1月1日の時点で成人であること
・受贈者が贈与を受けた年の合計所得額は2,000万円以下であること
また、この制度を利用する場合は、贈与税がかからない場合でも税務署に申告する必要があります。
【参照】国税庁「No.4508 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税」詳しくはこちら

住宅取得資金の贈与は課税される?非課税になるケースや注意点を解説

贈与税申告の手順とは?非課税の場合の申告や書類の書き方も解説
結婚・子育て資金の一括贈与
結婚・子育てのための資金を、父母や祖父母といった直系尊属から贈与された場合は、1,000万円まで(結婚関係の支払いは300万円まで)非課税になります。
制度を利用できる主な条件は以下の通りです。
出典・2015年4月1日〜2023年3月31日までの間に金融機関と結婚・子育て資金管理契約を結ぶこと
・管理契約を結んだ金融機関で専用口座を開設すること
・受贈者は、18歳以上50歳未満であること
・受贈者は、贈与される前年の合計所得額が1,000万円以内であること
また、贈与者が亡くなった場合や受贈者が50歳になった場合には、相続税や贈与税が発生する可能性があります。
なお、この特例が適用されるのは2023年3月31日まででしたが、2023年度(令和5年度)の税制改正大綱によると2年間延長される方針です。
【参照】国税庁「No.4511 直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の非課税」詳しくはこちら
【参照】総務省「令和5年度税制改正の大綱(PDF)」詳しくはこちら

結婚資金の贈与は300万円まで?概要と非課税枠について解説

贈与税がかからない「生前贈与」の非課税枠まとめ
まとめ
生前贈与には暦年課税と相続時精算課税の2つがあり、税負担を軽減する目的で利用されるのは主に暦年課税です。1年間の基礎控除額である110万円までであれば非課税となるため、うまく活用すれば相続時の税金を減らすことができます。
しかし、定期贈与や名義預金とみなされると贈与税や相続税がかかる可能性があるので注意が必要です。ほかにも教育資金や住宅取得資金、結婚・子育てに関わることであれば非課税で贈与できる場合があります。各制度を確認し、それぞれのケースにあわせて使い分けることをおすすめします。

みなし贈与とは?贈与税が発生する具体事例や対策方法を解説
ご留意事項
- 本稿に掲載の情報は、ライフプランや資産形成等に関する情報提供を目的としたものであり、特定の金融商品の取得・勧誘を目的としたものではありません。
- 本稿に掲載の情報は、執筆者の個人的見解であり、三菱UFJ信託銀行の見解を示すものではありません。
- 本稿に掲載の情報は執筆時点のものです。また、本稿は執筆者が各種の信頼できると考えられる情報源から作成しておりますが、その正確性・完全性について執筆者及び三菱UFJ信託銀行が保証するものではありません。
- 本稿に掲載の情報を利用したことにより発生するいかなる費用または損害等について、三菱UFJ信託銀行は一切責任を負いません。
- 本稿に掲載の情報に関するご質問には執筆者及び三菱UFJ信託銀行はお答えできませんので、あらかじめご了承ください。