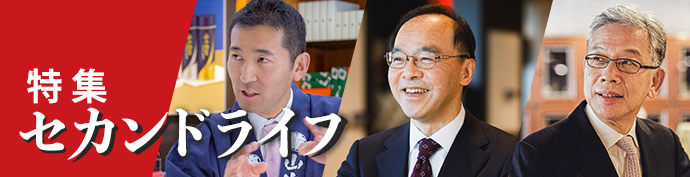相続で遺留分侵害額請求権の時効はいつまで?確実に遺産を受け取ろう
遺留分侵害額請求権には時効があり、請求権の行使時期によって異なります。今回は、遺留分侵害額請求権の時効、そもそも遺留分とは何か、請求手続きの方法や時効の除斥期間などを解説します。自身が受け取るべき相続財産を守るためにも遺留分侵害や時効について理解しましょう。

遺留分侵害額請求権とは?

被相続人(相続財産を残した人)が亡くなった場合、法定相続人(法律で定められている相続財産を受け取る人)には、最低限の割合で残された財産を受け取る権利があります。その権利を「遺留分」といいます。
例えば、被相続人のすべての財産を法定相続人以外の者に相続させるという遺言が残されていたとします。その財産は元々被相続人のものなので、被相続人が誰にいくら贈ろうとしてもそれ自体は問題ありません。ですが、被相続人の身内である法定相続人からすると、遺言の対象が法定相続人以外の者であった場合、「なぜ、自分たちは法定相続人なのに遺産をもらえないのか」という不満が生まれることでしょう。実際、相続という制度には「遺族の生活」や「その財産が作られる過程における貢献分を保障する」という目的もあります。そこで、被相続人の意思を尊重するとともに本来もらうべき法定相続人の権利も保護するために、こうした規定がなされています。

法定相続人はどんな順位できまる?遺産の取り分や例外での注意点を解説

遺言書の種類一覧と作成方法!種類別のメリットとデメリットも解説

遺贈にかかる税金の種類や計算方法とは?死因贈与との違いも解説
被相続人が生前行った贈与や遺贈(遺言により行われる贈与)により、本来もらえるはずの遺産をもらえない場合、法定相続人は遺留分を請求できます。この権利のことを「遺留分侵害額請求権」といいます。
ただし、法定相続人のうち第三順位(※)の「被相続人の兄弟姉妹および、その代襲相続人」には、この権利は認められていません。また「相続放棄」はもちろん、「相続欠格」「廃除」によって相続権を失った人にも認められていません。相続欠格や廃除に関しては、相続欠格や廃除によって相続権を失った人の子供のみが代襲相続人として遺産を受け取ることになります。
相続欠格は「相続を有利にするために殺人や詐欺・強迫・偽造などの犯罪行為をした者は、相続人になれない」という制度で、廃除は「被相続人の申し立てにより家庭裁判所が認めた場合、ある特定の人から相続の権利を奪うことができる」という制度です。相続欠格はすべての相続人が対象ですが、廃除は遺留分の権利を持つ相続人のみが対象です。
また、遺留分侵害額を請求できるのは「相続が開始された(被相続人が亡くなった)後」になります。存命中に遺留分を侵害するような贈与などが発覚したとしても、その時点で請求することはできません。
※第一順位は「直系卑属(子、孫等)」、第二順位は「直系尊属(親、祖父母等)」のことをいいます。

相続放棄とは?遺産の価値や限定承認も検討して放棄すべきか考えよう

相続人になれない?!「相続欠格」になる理由や事例などを解説
遺留分侵害額請求権の時効はいつまで?

もし仮に遺言書に法定相続人は遺産がもらえない内容が記載されていたとしても、遺留分があれば遺留分侵害額請求権を行使でき、最低限の遺産を受け取ることができます。しかし、遺留分請求権には「時効」があり、時効を過ぎてしまった場合は、遺留分を受け取ることができなくなるので、注意しなければなりません。
遺留分があることを知った時から1年
遺留分侵害額請求権の時効については「民法第1048条」において、以下のように規定されています。
出典第1048条 遺留分侵害額の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から一年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から十年を経過したときも、同様とする。
【参考】電子政府の総合窓口 e-gov「民法」詳しくはこちら
つまり、「相続が開始され、遺留分すら渡してもらえない可能性がある」ことが分かったら、「その日から1年以内に遺留分侵害額請求権を行使しなければ、以後は遺留分を請求できなくなる」ということです。ただし、これはあくまで「知った時から1年間」なので、たとえば「亡くなって3年経ってから、その事実を知った」というような場合は、「その時点から1年間」ということになります。
相続が発生してから10年
法令が示すように、遺留分侵害額請求権には1年の時効以外にも10年という「除斥期間」も定められています。除斥期間というのは「何かの権利を持っていても、その間に行使しなければ、その権利が自動的に消滅してしまう」期間のことです。時効と違って、中断できません。
この規定により「しばらく疎遠になっていた」など、さまざまな事情により「亡くなったことを知らなかった」という場合でも、相続開始から10年経ってしまうと遺留分請求権を行使できなくなってしまいます。
遺留分侵害額請求権の時効を止める方法

遺留分が侵害されていると分かってから時効までは1年しかありませんので、のんびり構えているとあっという間に時効を迎えてしまいます。これを防ぐためには、時効の「完成猶予・更新」を行って、1年で時効が完成しないようにしなければなりません。
ここでは、時効を遅らせるための方法を4点ご紹介します。
①内容証明郵便で意思表示
遺留分の侵害を認識した場合、まずは内容証明郵便で意思表示をすることをおすすめします。意志表示とは、「遺産を相続または遺贈を受けた人に遺留分を侵害していること伝える」ことで成立します。ただし、口頭や電話、メール、普通郵便などの手段では「そんな話は聞いていない」と後から否定されてしまう可能性があるため、「内容証明郵便」の方法を利用して記録に残るようにします。
内容証明郵便を利用すれば、「いつ、どのような内容の文書を、誰が誰に対して郵送したか」ということを郵便局が証明してくれます。
②裁判外での交渉を行う
内容証明を郵送した後は、遺留分を侵害している相手側と直に交渉を行います。この時、スムーズに交渉が行われて解決すれば良いですが、必ずしもそうとは限りません。遺産範囲、評価などに関して問題が発生することも多々あるため、交渉内容を録音などの手段も使って記録しておきましょう。
交渉がうまくいった場合は、合意書を取り交わして支払いをしてもらいますが、うまくいかなかった場合は請求調停によって裁判所での話し合いが必要です。
③合意書を取り交わす
遺留分侵害額請求の交渉がうまくいった場合には、後々のトラブルを防ぐために合意書を作成します。これは内容証明と同じく、後々「そのような約束はしていない」と言われて約束を反故にされることを防ぐ目的があります。
私文書としても作成可能ですが、一番は公証役場での公正証書による合意書を作成することをおすすめします。これを作成しておけば、後日合意して決まった金銭の支払いが滞った場合にも、裁判所の手続きをしなくても強制執行を行うができます。

遺産相続のトラブルの主な5つの原因とは?事前対策や解決方法を紹介
④遺留分侵害額の請求調停を行う
遺留分侵害額請求の交渉が決裂した場合は裁判所で争わなくてはなりませんが、特別な場合(裁判所が調停での解決はできないと判断した場合)を除いてすぐに訴訟はできません。最初に家庭裁判所で調停手続きを行い、裁判官と調停委員の仲介の元に話し合いをします。
手続きは、裁判所でもらえる申立書、または裁判所のHPからダウンロードした申立書と以下の必要書類を用意します。
出典・相続人全員の戸籍謄本
・被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍
・遺言書(公正証書遺言以外の場合には検認調書謄本の写しも必要)
・遺産に関する証明書等
・被相続人の子供、代襲者で死亡人がいる場合はその人の出生時から死亡時までの戸籍謄本
・相続人に被相続人の父母がいて、どちらかが死亡している場合、死亡記載のある戸籍謄本
これらを用意したら、相手方の住所地にある家庭裁判所か当事者間で合意した家庭裁判所のどちらかに提出して申し立てをします。また、前段階の交渉をせずに、調停申し立てをすることも可能ですが、調停を申し立てただけでは遺留分侵害額請求の意思表示とはなりません。相手のアクションがなければ時効が成立する可能性もあるので、調停の前段階で交渉を行っておくことが重要でしょう。
遺留分侵害額請求権を行使した後の時効は5年

遺留分侵害額請求権の行使後、当該請求権は金銭債権として、「債権一般の消滅時効」が適用されることになります。そのため遺留分侵害額請求後、5年の時効期間を経過してしまうと、金銭請求としての権利が消滅するので遺留分の確保ができないことになります。
時間をかけて意思表示や交渉、訴訟まで行ってきたのに、時効の成立で遺留分が確保できなくては元も子もありません。支払完了まで気を抜かず、最後まで時効に気をつけましょう。
また、時効期間は現在5年ですが、これは令和2年4月1日に施行された改正民法がきっかけです。それ以前は時効期間が10年でした。そのため、請求権の行使がいつ行われたかによって、以下のように時効が変わります。
・令和2年3月31日以前の行使:時効10年
・令和2年4月1日以後の行使:時効5年
まとめ

相続における遺留分に関する時効はいくつかありますが、最短で1年です。1年は長いようで短い時間なので、遺留分が侵害されていることに気づいたら、直ちに内容証明で意思表示を行うようにしましょう。これにより遺留分侵害額請求の効果は発生するため、その後当事者同士でじっくり話し合えば、納得のいく解決方法もみえてくるはずです。また、遺留分を受け取ることになった際は、金銭の支払いまでの間にも時効があることに留意しましょう。

相続遺留分を放棄する理由とは?相続放棄との違いや注意点を解説
ご留意事項
- 本稿に掲載の情報は、ライフプランや資産形成等に関する情報提供を目的としたものであり、特定の金融商品の取得・勧誘を目的としたものではありません。
- 本稿に掲載の情報は、執筆者の個人的見解であり、三菱UFJ信託銀行の見解を示すものではありません。
- 本稿に掲載の情報は執筆時点のものです。また、本稿は執筆者が各種の信頼できると考えられる情報源から作成しておりますが、その正確性・完全性について執筆者及び三菱UFJ信託銀行が保証するものではありません。
- 本稿に掲載の情報を利用したことにより発生するいかなる費用または損害等について、三菱UFJ信託銀行は一切責任を負いません。
- 本稿に掲載の情報に関するご質問には執筆者及び三菱UFJ信託銀行はお答えできませんので、あらかじめご了承ください。