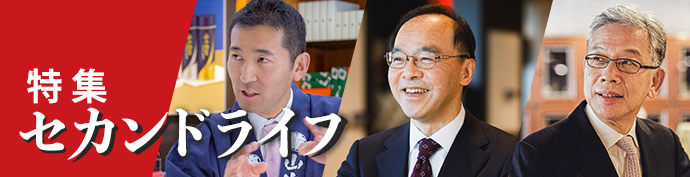企業オーナー必見!「事業承継」の基本やメリット・デメリットを解説
経営者が自分の事業を後継者に引き継ぐ「事業承継」の基本を知ることで、いつか身を引くときにも望ましい形で引き継ぎを行うことができます。今回は、事業承継に関する基本的なポイントを紹介します。事業承継の種類ごとのメリット・デメリットや流れを押さえておきましょう。

事業承継とは

経営者が自分の事業を後継者に引き継ぐことを、事業承継といいます。
承継とは、一般的に「先代から何かを受け継ぐこと」を意味します。身分・地位・事業などの具体的なものだけでなく、理念・伝統といった抽象的なものまで、広い範囲を対象として受け継ぐことを指します。
事業承継では、単に経営者としての地位や事業を引き渡すだけでなく、株式をはじめとする各種資産や権利も承継します。経営者の生前に株式の承継が行われた場合、税務上は贈与や譲渡として取り扱われます。一方、経営者の死によって株式の承継が行われた場合は、相続として取り扱われます。それぞれのケースで贈与税または相続税といった税金が生じる場合があります。
混同されやすい用語として「事業継承」と「事業譲渡」があります。まずはその2つとの違いを確認しましょう。
事業継承との違い
「承継」と「継承」は近い意味を持ちますが、厳密には異なる語として使い分けられます。
継承は「義務・財産・権利を受け継ぐ」ことを意味し、承継のように理念や伝統までは含まれません。
そのため、事業承継を用いる場合は「先代の理念・伝統などの精神的な面を受け継ぐ」という意味合いが強調されます。一方、事業継承は「先代の経営権や株式などを引き継ぎつつ、理念は刷新する」といった状況で使われます。
このような使い分けは厳密に決められているわけではありません。税制などの法律的には事業承継が使われていることから、事業継承に当たるような場合でも慣例的に事業承継を用いられることがあります。
事業譲渡との違い

事業譲渡は「会社の事業の全てまたは一部を譲り渡すこと」を指します。経営権や株式を他者に渡すという点では事業継承と同じですが、株式の売却といった取引によって譲渡され、売り手が資金を得られる点に違いがあります。
事業譲渡のプロセスは、社外の買い手と譲渡範囲や条件などについて合意書を締結したのち、株主総会特別決議での承認や事業譲渡契約書の締結などいくつかのステップで進めていきます。
なお、事業承継にも会社法の規定が存在します。こうした規定を遵守することで、実質上の事業譲渡として事業承継が行われるケースも少なくありません。
事業承継の重要性
特に中小企業において、事業承継を滞りなく進めることは喫緊の課題です。2021年の日本商工会議所のアンケートによると、中小企業経営者のうち約2割は、後継者が不在だと回答しています。またその2割のうち、48.6%は黒字企業でした(※1)。このことから「黒字経営がなされており継続したいにもかかわらず、後継者不足で廃業せざるを得ない」という中小企業が多いことが分かります。
他方で中小企業は、国内企業の99%を占め、国から「我が国経済・社会の基盤を支える存在」(※2)とまでいわれています。こうした中小企業をこれからも長く存続させていくことは、日本の経済・社会全体の生命線とも考えられます。実際に中小企業庁などによって、様々な事業承継支援策が整えられています。
※1【参照】日本商工会議所『「事業承継と事業再編・統合の実態に関するアンケート」調査結果について』詳しくはこちら
※2【参照】中小企業庁「事業承継ガイドライン 第3版(PDF)」詳しくはこちら

【特集 セカンドライフ】第2回 生涯現役、目に見えない資産を次世代に伝えたい~山本 貴大さん〜
事業承継で引き継ぐ資源

事業承継により後継者へ引き継がれるものは、主に「人・経営権」「資産」「知的財産」の3つに分けられます。これら要素を具体的に把握しておきましょう。
人・経営権
「先代から後継者へと経営者が交代すること」を指して「人の承継」と呼ばれます。すなわち「経営権の承継」です。
しかし単に経営権を渡すだけでは、適切な人の承継とはならないケースもあります。中小企業などでは、現経営者一人に業務のノウハウや従業員との信頼関係、重要顧客との信頼関係などが集約されていることも少なくありません。
そのため、それらを適切に引き継ぐには、後継者を充分に育成し、社内外との信頼関係を継続できる状態にする必要があります。
特に親族が承継するケースでは、早めの候補者選定と育成が重要です。新経営者が、業務ノウハウだけではなく、企業の理念や存在意義を受け継ぐことができなかった場合、従業員や重要顧客からの信頼は低下しやすくなるでしょう。
資産
現経営者が所有している自社株式や、企業の資金などを後継者が受け継ぐことを「資産の承継」と呼びます。事業用の設備や不動産、許認可、また借入金も資産として承継されます。
注意点として、新経営者は2/3以上の株式を承継していなくては、安定した経営権を保持できません。例えば、家族経営の企業などで、現経営者が自社株式を複数の子供に分割して譲渡しようとしているケースでは、経営権を一人に集約することが難しくなる恐れがあります。
また親族を新経営者とする資産承継時には、贈与税・相続税も考慮しなくてはなりません。株式評価額によっては、高額の納税が必要になることがあります。後述の税制上の優遇措置などを活用し、こうした負担を可能な限り軽減することが資産承継のポイントです。

株式を相続する方法や税金の計算方法を解説!非上場株式との違いとは
知的財産
特許として保有する知的財産の他にも、ブランド力や特許として公開していない技術、また特有の経営方針・理念などを受け継がせることが、「知的財産の承継」です。この知的財産には、取引先や顧客とのネットワーク、顧客情報、従業員たちのスキルやノウハウなども含まれます。
新経営者が、こうした知的財産をどれだけ重要視するかによって、承継後の企業のあり方は大きく変わります。それにより、顧客・従業員たちが会社に抱く心境も変化するでしょう。一般に、知的財産を大切に扱ってくれる後継者を選ぶことで、顧客・従業員に不信感を抱かせず、スムーズに事業承継ができます。
誰に引き継ぐ?事業承継の種類

事業承継は、誰を承継相手とするかによって、3種類に分けられます。「親族」「社内従業員」「社外の第三者」を承継相手にする場合のそれぞれのメリット・デメリットを紹介します。
税制上の優遇措置を活用できる親族内承継
親族への承継は、例えば子供や配偶者などが後継者となる方法です。この場合、株式を承継する手段としては贈与や譲渡(売却)の他、経営者が亡くなったときには相続による承継も考えられます。
親族内承継のメリット
親族内承継では、一定の要件を満たす場合には贈与税の納税を猶予することができ、さらに猶予された贈与税の納付が免除される場合があるという点がメリットでしょう。株式の移転の手法として贈与が多く用いられますが、株式を受け取った受贈者側で贈与税が高額となることが問題となるケースがあります。このような場合、法人版事業承継税制を利用すれば、先代から後継者へ非公開株式が贈与された場合に一定の要件を満たすと贈与税の納税を猶予することができます。また、贈与者である先代の死去などの一定の条件を満たすことで猶予された贈与税の納付が免除されます。
適用の条件は細かく定められているため、この制度の具体的な手続き方法については、国税庁の案内を確認してください。
また、個人の事業用資産の承継にかかわる贈与税や相続税を猶予・免除できる個人版事業承継税制もあります。
その他にも、後継者を教育しやすく、社内外の関係者に混乱を生じさせづらいこともメリットです。例えば、後継候補者である親族を若いうちから雇い、様々な部門を経験させ、他の従業員と同様に段階を経て責任あるポストまで育てます。血縁関係がある上に後継候補者が教育期間中に社内外の関係者と善良な関係を築いていれば、滞りなく承継できます。
【参考】国税庁「法人版事業承継税制」詳しくはこちら
【参考】国税庁「個人版事業承継税制」詳しくはこちら
親族内承継のデメリット
複数の後継候補者や相続人(子供など)が存在する場合には、後継候補者の選定が難しくなります。安定した経営のために自社の株式の2/3以上を新経営者に承継させるには、親族間での株式の分配に注意が必要です。複数人を候補としていた場合、選定されなかった人へのフォローを考えておかないと、親族内での争いに発展しかねません。
逆に、後継候補者として適格な親族がいないことも少なくありません。たとえ後継候補者を若いうちから自社で育てていたとしても、当人の意思で承継を拒否される可能性もあります。
会社に詳しい人材に任せられる社内事業承継

社内事業承継は自社の従業員に事業を承継することを指し、従業員承継とも呼ばれます。経営者の右腕として活躍している役員など、経営者と親しくかつ責任あるポジションに就いている人物に承継されます。
また、親族内承継へのつなぎとして一時的な社内事業継承を行うケースもあります。この場合、経営者一族は自社の株式を保有したまま社長のポジションだけが後継者に承継されます。
社内事業承継のメリット
実際の業績や意欲、姿勢などを総合的に評価して後継者を選定できる点が大きなメリットです。自社に長期間勤めている従業員であれば、実務遂行能力に加え、取引先や顧客からも厚い信頼を獲得している可能性があります。このような従業員を後継者とすれば、社内外の関係者からも納得を得られやすいでしょう。
社内事業承継のデメリット
社内事業承継の場合には一般的に有償譲渡により行われるため、後継者は自社株式を自分で購入しなくてはいけません。贈与により株式を取得する場合でも、贈与税がかかります。そのため、後継者側の金銭的負担が非常に大きくなり、株式の評価によっては、高額の資金を調達する必要があります。
また経営者が後継者に株式を譲渡せずに、社長のポジションのみを譲った場合、後継者が迅速な意思決定をできないことから事業に混乱が生じやすくなるといえます。オーナーである元経営者と後継者の間で経営方針に差異が生じた場合、社内外を巻き込むトラブルに発展する恐れもあるでしょう。
会社の可能性が広がる第三者への承継(M&A等)

社外の人物に経営権を承継する方法が「第三者への承継」です。合併(Mergers)や買収(Acquisitions)によって他企業に自社株式を売却し経営権を渡すことを「M&A」と呼びます。
第三者への承継のメリット
親族・社内に後継者がいなくても、広い視野で社外から適任者を探すことができます。自社のポテンシャルを引き出してくれる後継者を見つけることができれば、自社のさらなる飛躍が期待できるでしょう。
また有名な企業やファンドに経営権を売却できれば、その事実によって自社のブランド力向上にも繋がります。結果、売上や株式価値の向上などで経営基盤が強化されたり、従業員たちの活躍の場が増えたりと、自社の可能性が広がります。
また株式を売却することで、元経営者が利益を得られることもメリットです。同時に、金融機関から自社が受けている融資も、他社・ファンドへ引き継がれます。これによって、元経営者は個人保証からも免責されます。
第三者への承継のデメリット
M&A専門の仲介業者などを上手く活用しないと、最適な後継先を探すことは困難です。また一般に、後継予定の第三者(企業やファンド)と非常に細かい交渉を忍耐強く続けなくては、理想的な承継は実現しません。
例えば、従業員たちへの扱いや雇用条件が、承継前から大きく変更されるケースもあります。M&Aによってほぼ別の会社になってしまうこともあるため、経営の一体性や企業風土を保ったまま会社を残したいのであれば、慎重に検討したほうが良いでしょう。
事業承継のステップ

適切な事業承継を実施するには、事業継承計画書を策定する必要があります。10年ほどの承継スケジュールを組み、詳細な計画を立てます。
具体的なプロセスとしては、以下の3つのステップで把握しましょう。
①会社の現状を把握して、後継者を選定
企業の健康診断ツールともいわれているローカルベンチマークを活用して、現在の経営状況を「見える化」します。これによって、現状で自社が「どれくらいの競争力を持っているか」また「どんな課題を抱えており、その解決にはどんな努力が必要か」を明確にしましょう。
特に、従業員たちが培ってきたノウハウや、取引先・顧客とのネットワークなどについても明らかにし、自社の知的財産として具体的に把握してください。これには、知的資産経営報告書の作成も有効です。
こうして現状把握を進めつつ、自社の課題解決や、知的財産を有意義に保存・活用できるような後継者を探しましょう。なお、事業承継を目指す経営者のために、商工会議所などが主催するセミナーが定期的に開催されているので、積極的に参加してみてください。
②会社を磨き挙げ、価値を高める
後継者側に「自社を承継したい」と思ってもらうため、自社の価値向上を目指しましょう。特にM&Aなどによる経営権の譲渡を目指す場合には、このステップは非常に重要です。
自社を磨き上げ、株式評価を上昇させるには、自社が抱えている課題を解決することが有効です。上述のステップ①で明確にした課題や自社の強みを振り返り、具体的な解決策を実施しましょう。例えば、「業務フローの効率化」「人材育成の実施または強化」「新規顧客獲得へのアプローチ」など、自社の現状に即した改善策を推進してください。
同時に、経営者自身の権限を各役員へ移譲するなどで経営リスクを分散させておくことや、不必要な資産があれば処分しておくことも推奨されます。これによって、後継者の負担を少しでも抑えましょう。
③事業承継計画書の策定

事業承継計画書の作成方法や書式は法的に定められてはいません。基本的には10年ほどのスケジュールを設定して、承継プロセスを具体化します。
後継者と認識をすり合わせながら、共同でスケジュールを策定していくと、承継を行う際にスムーズになります。
事業承継計画書では、後継者の育成プランや、現経営者の引退タイミングなども含め、人・資産・知的財産をどう承継するのかを明記します。完成した事業承継計画書を社内外の関係者や金融機関とも共有すれば、後継者が円滑に経営を開始できます。
悩んだ場合は早めに相談を
事業承継計画書の策定自体やそれまでのステップには、多くの時間・労力を割かなければなりません。そのため、早めに取り組むことが何よりも大切です。ここまでに挙げたステップや第三者との事前交渉などを適切に進めるには、様々な専門知識が必要です。税理士・公認会計士や金融機関など、自社とつながりが深い相手に相談してみましょう。
相談相手が身近にいない場合は、民間のM&A仲介会社や、国や自治体の支援機関、商工会議所の専用窓口などに頼ることもおすすめです。事業承継には10年ほどの時間がかかる場合もありますので、ぜひ早めに相談してください。
まとめ
事業承継とは、身分・地位・事業などの具体的なものだけでなく、理念・伝統といった抽象的なものまで、広い範囲を対象として受け継ぐことを指します。承継相手にかかわらず、事業承継には専門知識を必要とし、時間がかかります。
後継者が親族・従業員の中には見つからないケースも多く、「中小企業における後継ぎの不在」は、日本社会全体の問題になっています。そこで、今日では税制度の設置や、各種セミナーの開催などを通じて、中小企業の事業承継を促進する流れが活発化しています。
経営者としての判断力や手腕が衰えないうちに、ぜひこうした税制・セミナーを利用しつつ、事業承継の準備を始めてください。
ご留意事項
- 本稿に掲載の情報は、ライフプランや資産形成等に関する情報提供を目的としたものであり、特定の金融商品の取得・勧誘を目的としたものではありません。
- 本稿に掲載の情報は、執筆者の個人的見解であり、三菱UFJ信託銀行の見解を示すものではありません。
- 本稿に掲載の情報は執筆時点のものです。また、本稿は執筆者が各種の信頼できると考えられる情報源から作成しておりますが、その正確性・完全性について執筆者及び三菱UFJ信託銀行が保証するものではありません。
- 本稿に掲載の情報を利用したことにより発生するいかなる費用または損害等について、三菱UFJ信託銀行は一切責任を負いません。
- 本稿に掲載の情報に関するご質問には執筆者及び三菱UFJ信託銀行はお答えできませんので、あらかじめご了承ください。